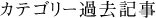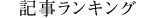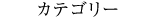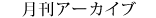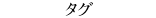カテゴリー:日本文化と笹

松竹梅とは、松と竹と梅。お正月飾り門松や鏡餅など、めでたいものとして祝い事の景物などに使われます。品物などを三階級に分けた際の等級の呼称で、一般的には松が一番で竹、梅の順となります。竹を使用した門松はお正月の縁起物として一般的です。
松竹梅の由来は諸説ある中で「歳寒三友(さいかんさんゆう)」が最も有名です。
「松と竹は寒中にも色褪せず、また梅は寒中に花開く」
冬の寒い季節に友とすべき三つのもの、という意味がこめられています。
それにしても、なぜ松が一番良くて、その後に竹、梅と続くのか?こちらも諸説ありますが
今回は少し変わったセクシャルな「松竹梅」の由来をお話します。
「松」
縁起ものは決まってお祭りに使われていますが、この祭りそのものがセクシャルな崇拝から始まったことがそもそもの始まりでした。
私たちの祖先の権力者は、指導的な地位を確保するに従って老境に入り、子供を作ることが難しくなっていくと、その「復活」を願い、長寿の植物にあやかろうと必死になって祈ったそうです。
その第一が松でした。ここに「松竹梅」の松が一番始めにくる理由があります。
松の古名は又(また)といいます。なぜ又と言われるかというと、松の新芽は虫害や風害などで節間を短く切られるようなことがあると、2枚の針葉の間から新しい芽が生えてくることがあるためです。この2枚の「葉」を足に、新しく生えてくる「芽」を産まれてくる子供に見立て、この出生にあやかろうと、新芽に願いをかけました。
松を祭り木として、大切に祈りの対象にしたのは平安時代からです。当時、権力者は今日という門松を立てたり、「若松」といって床に立て、新年を寿(ことほ)ぎ、合わせて老人の精力の永続を祈願しました。
そして、神社域に松を植えて飾り、神々永遠の性を願ったそうです。そのような神聖な松の木は(主に巨木)「又の木」から転じて「祭りの木」すなわち「マツの木」としたり、公木にみたてて、木偏に公と書いて「松」の字としました。
松は子孫の繁栄に縁起の良い植物なのです。
おそ松くんに兄弟が多いのも、この松の恩恵に授かったためかもしれません。
「竹」
竹は鎌倉時代から登場しました。人々はあらゆる生物の中で筍が急速に成長するのをみて驚き、松に続き祈りの対象としたそうです。
筍は1日に1~2メートル成長します。老人たちはこの筍の成長力をうらやましく思ったのでしょう。これにもあやかりたいと「復活」を願ったそうです。祈りでは、できるだけ大きな筍を選び「ご神体」に納めたといいます。筍はあっという間に成長して、その皮だけ残し竹となります。その成長力を見た老人たちは、いっそう神秘性を感じたのかもしれません。
「梅」
その後、徳川時代になって奇数がおめでたいと言われるようになりました。そこで「松」「竹」に加えられたのが「梅」。「梅には自然にそなわった気品と風流がある」ということや語呂が良いことで「梅」が選ばれました。
ですが、「梅」は「松竹」とはもともと起源が違う異質のもので、調和を欠いているため、しばしば「梅」を除いて「松竹」と組んだだけで用をなしてしまうシーンもあります。松竹の組み合わせでもおめでたさには変わりがなく、不自然ではありません。
門松を飾らない理由
また、お正月に門松を立てないという家もあります。そうした家では先祖が門松か、あるいは氏神(うじがみ)様の門松や、床の間の門松で目を突いて怪我をした先祖であると考えられています。
竹は1節から2本の枝が出て、短い枝の出る側を表、長い枝が出る側を裏といいます。門松を飾るとき、竹の表を正面に向けるのは、このような事故を踏まえての「怪我をしないように」という思いやりからであると言われています。
鏡餅の由来
鏡餅に添えられるウラジロも深い意味合いを持っています。
これも老人たちの「復活」の願いを託された植物でした。向かい合った2本の葉の主軸に生えた黒い毛に包まれたような芽を男性のシンボルにみたて、その再起を祭るため緑の方を上向きに葉は白い側が上にして餅を積みます。ですので、白い側を下側にするとシンボルが下向きになってしまい願いが叶わなくなってしまいますので、男性の方は気をつけましょう。
鏡餅の飾り始めは12月28日が縁起が良いとされています。29日は9(苦)がつくため避けられます。鏡開きは1月11日に行うのが、「111」とゾロ目になるため縁起が良いとされています。
また、門松も28日までに飾ると良いとされています。